オリンピックの開会式での歌舞伎役者・市川海老蔵さんとジャズピアニスト上原ひろみさんの共演ご覧になりましたか?
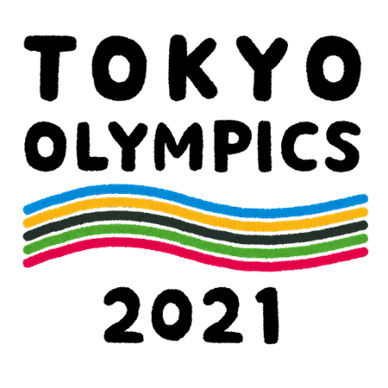
「歌舞伎」を見た事がない方にとっても、
正にTHE KABUKIというイメージの力強い大迫力のパフォーマンスでしたよね。
とは言うものの、
あれは何を表現しているの?
「しばらく」とはどう言う意味?
どうしてあんなに強そうな化粧をしているの?
疑問がある方も沢山いらっしゃると思います。
今回はオリンピックの歌舞伎パフォーマンスの謎を解きながら、 歌舞伎の歴史やスタイルなどを分かりやすく解説していきます
スーパーヒーローの物語「暫(しばらく)」

オリンピックで海老蔵さんが演じたのは、
伝統的な演目「暫(しばらく)」というものです。
内容は簡単に説明するとスーパーヒーローの物語です。
権力者(清原竹衡)が自分に従わない人たちを殺すように家来に命じた時、
そこへスーパーヒーロー(鎌倉権五郎景政)が「しばらくー!」と声を上げながら登場、
人々の命を救います。
「しばらく」とはどう言う意味?

現代では使わない言葉も多い歌舞伎のセリフ。
なぜなら、「暫」は今から約300年以上前に初演されたからです。
今日急に誰かに「しばらく!」と言われたら、
「しばらく会ってなかったね。」というような意味で使われると思います。
しかし、歌舞伎の演目では意味が異なります。
「しばらく待て!(ちょっと待て!)」という意味です。
悪人の悪さを、威勢よく引き止めます。
主人公は18歳頃の若者です。
力強い若者が権力者に立ち向かい弱者を助けるストーリーが大人気になった背景には、
この演目が生まれた地域や人々の特徴が関わっています。
江戸で大人気!荒々しい歌舞伎「荒事」

「暫」が生まれたのは元禄年間(17世紀後半〜18世紀前半)の江戸。
江戸には当時、多くの人が新しい生活を期待し集まり、武士も多く、
活気のある派手なものが好まれていました。
荒々しいヒーロー物語が江戸の町人の心を射とめたことも納得ですね。
豪快で力強い歌舞伎の表現方法が江戸では発達し、
「荒事(あらごと)」と呼ばれます。
荒事には見得や六法、隈取りの化粧法など現代でも歌舞伎のイメージを象徴するような技法も多く含まれています。
例えば隈取りの化粧。
キャラクターの豪快で強いイメージを表現すると共に、
当時は劇場の照明が今より暗いですから客席から良く見える工夫でもありました。
荒事は初代市川團十郎によって人気になり、
二代目市川團十郎によって成立します。
その後も代々続く役者も荒事を最も得意とした為、
市川家のお家芸として選んだ演目18選「歌舞伎十八番」はほとんどが荒事です。
オリンピックでパフォーマンスをした海老蔵さんは
正確には「十一代目市川海老蔵」。
市川家の芸を伝承する歌舞伎役者の一人です。
上方では気品ある歌舞伎「和事」が好まれる

一方同じく元禄時代にもう一つの歌舞伎の表現方法が生まれます。
新しい都市「江戸」とは打って変わり、
既に洗練された都市であった「上方」が発祥です。
「荒事」と対照的な「和事」です。
「上方」とは現在の京都や大阪を指します。
上方では古くから既に文化や芸術が発展してきていた為、
人々は奇抜で派手な表現より、柔らかな小洒落た表現を好みました。
そこで人気になった歌舞伎表現が「和事(わごと)」です。
和事では、色っぽいやさ男がしなやかに表現されます。
身分の高い男が、落ちぶれながらも遊女へ通う姿などが人気でした。
初代坂田藤十郎により特に和事の人気は上がり、現在でも上方の芸風として親しまれています。
同じ時代の歌舞伎でも、
地域によってこれほど人気が分かれるとは興味深いですね。
日常でも使われているあの言葉。実は歌舞伎から?

今回ご紹介した「暫」の台詞のように
現代人には馴染みのない言葉が多く出てくる歌舞伎。
でも実は私たちが何気なく使っている表現で
歌舞伎をルーツに持つ言葉もたくさんあります。
カラオケで「おはこを歌ってよ。」
なんて話したりしますよね。
おはこ=得意なもの
「オハコ? 」
実はこれ「十八番(おはこ)」と書きます。
そう。歌舞伎十八番から由来しています。
オリンピック開会式から歌舞伎の世界へ

いかがでしたか、オリンピックの歌舞伎パフォーマンスから紐解く歌舞伎の世界。
「暫」は豪快なスーパーヒーローのお話。
江戸と上方では好みも全くちがう「荒事」と「和事」
難しそうな歌舞伎の言葉も、意外と身近にある「十八番・おはこ」
歌舞伎の楽しみ方は皆さんそれぞれです。
興味のあるポイントをみつけて、是非歌舞伎を観に行ってくださいね。
京都着物レンタル 和凛では、
大人のお出かけにおすすめの、正絹の着物レンタルプランをご用意しています。
上質な正絹の着物は、伝統のある南座の雰囲気にピッタリ!
いつもよりちょっと背伸びしたおしゃれで、初めての歌舞伎を楽しんでみませんか?
